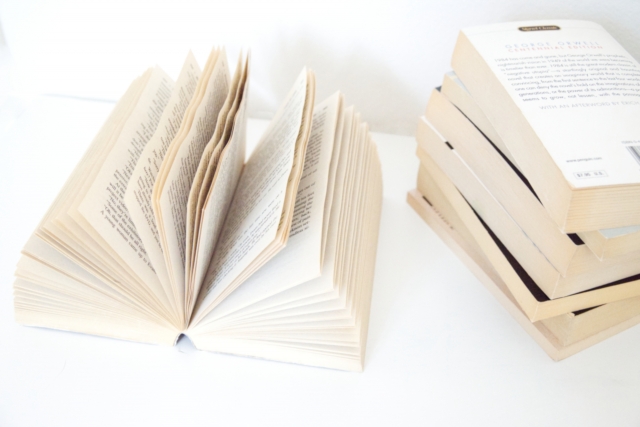こんにちは。
今日7月29日は「7(なぞ)2(に)9(く)」で「謎肉の日」。
この日はカップヌードルでおなじみの日清食品が制定した「謎肉」の記念日。そう、あの四角い肉のような何か…
正式名称は「味付豚ミンチ」というそうで、以前は「ダイスミンチ」と言っていたそうです。
ネット界隈ではその独特な食感と「何からできているのか分からない感」から「謎の肉」「あの肉」「謎肉」などと呼ばれていました。
今では「謎肉」は公式の通称となっていますね。
流石尖ったプロモーションの日清食品です。懐が深い(笑)
今や「謎」ではなくなったその肉の正体は、「大豆たん白や豚肉などをミックスした加工肉食品」。謎だった時代(?)が逆に懐かしいような気もします(笑)
・「何からできているか」を知るということ
「謎肉」が身体に悪いとか、そういった話ではありません。しかし加工食品であることには変わりありません。
加工食品は、日々の生活に欠かせません。保存が効いてすぐ食べられるような加工食品は、なんだかんだ重宝しますよね。
しかしそれが何からできているのか、どんな工程を経て作られたのかを、意外と我々は知りません。
食品添加物、香料、保存料、たん白加水分解物……原材料名の欄に並ぶこれらの言葉は、読み慣れないままスルーしてしまうことも多いのではないでしょうか。
そして「添加物」とあるだけで毛嫌いしてしまう…
しかし「知ること」こそが第一歩。正体がわからないから怖いのであって、知ってみれば意外と理にかなっていることもあるのです。
そして「知ること」の第一歩として、以前の記事「商品表示を見る習慣のおススメ」にも書いた通り、
「成分表」を確認することはとても良いことだと思います。
謎肉が「大豆ミートと豚肉の融合体」だとわかれば、むしろタンパク源としてありがたく思えるかもしれません。
・食の安全とは「選ぶ自由」を持つこと
食の安全とは、「すべて自然由来であること」や「無添加であること」だけでは無いと思います。
勿論、自然のモノをそのままいただくことが自然であり、一番だと思います。
だけど日常の食から「添加物」を無くすのは至難の業になってしまいました。
そんな時代の食の安全とは、その食品の背景を知り、自分で選べること。つまり「情報にアクセスできること」だと思います。
そしてその情報を元に、我々が自由に「選ぶ」こと。
食品が配給制であったら選ぶことも出来ません。そして情報が遮断若しくは少ないようでしたら、判断も出来ません。
それこそが「食の安全保障」だと思います。
「謎のままでも楽しかった」時代から、「成分を公表することが信頼を生む」時代へ。企業と消費者の関係もまた進化してきました。
私たちも「何を買うか」だけでなく「何を選ばないか」も含めて、食卓の主導権を握る意識が大切なんだと思います。
食とはやがて身体になるものなのです。
・「未来の謎肉」は、培養肉や昆虫食か?
世界では培養肉(研究室で育てた細胞由来の肉)や昆虫食が注目されています。
食糧問題、環境問題への解決策として期待されているこれらの「次世代食」「代用食」は、
今の私たちにとっては十分「謎」に感じるかもしれません。
「大豆ミート」だって知らないひとからみたら「謎肉」とも言えるのかも知れませんし(笑)
※大豆ミートをディスってる訳ではありません。
しかし数十年後、次の世代がそれを当たり前に食べて「これが昔は“謎”だったんだよ」と話しているかもしれませんね。
それでも「昆虫食」はちょっと食べられる自信が無いなぁ…
最後までお読みいただきありがとうございます!