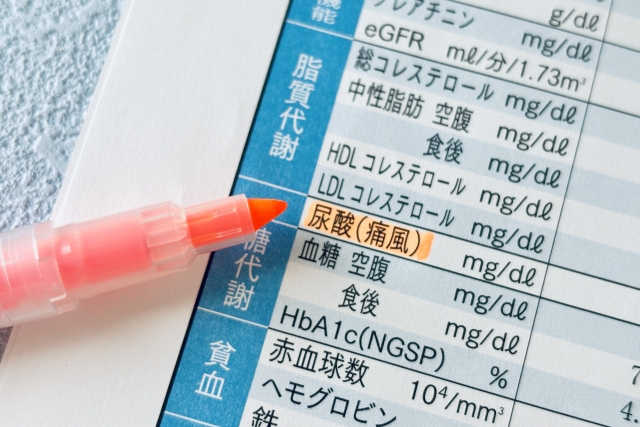こんにちは。
今日2月20日は「アレルギーの日」だそうです。
1966年の今日、免疫学者の石坂公成さんがアレルギーの原因となる抗体の一種、免疫グロブリンE(IgE)を発見したことに因んでいます。
絶賛花粉症中の世の中ですが、たまにご高齢のかたに「昔は花粉症なんてなかった」というお話を聞きます。
また特定の食材を食べられない「〇〇アレルギー」をお持ちのかたも多く、それを「甘え」や「食べさせれば治る」などという偏見や誤解も未だにあったりします。
※アレルギーは命に関わります。「甘え」とか「食べ続ければ治る」なんて無理をしてはいけません!
・なぜアレルギー患者が増えたのか?
昔からハチなどの毒のアレルギーは知られていました。しかし花粉症に代表される「アレルギー疾患」が取りざたされるようになってきたのは主に第二次世界大戦後です。
背景には「衛生仮説」という考えがあります。
・衛生仮説って?
簡単に言えば「社会が清潔になりすぎたこと」
昔から人類は細菌やウイルスなどによる感染症や伝染病の脅威に晒されていて、沢山の命が失われてきました。
第二次世界大戦後(というのも興味深いのですが)、欧米や日本(所謂今日の先進国)では衛生状態が大きく改善。
またワクチンなども発達して、感染症や伝染病での死者数が激減。
喜ばしいことなのですが、元々人間には免疫系が備わっていて、身体に入ってくる病原体を攻撃して守っていたのですが、
その攻撃対象が過剰とも言える衛生状態改善で少なくなってきたことにより、本来攻撃する必要の無い物質を「アレルゲン(アレルギー原因物質)」として過剰反応するようになったのです。
・どろんこ遊び
東西ドイツ合併後、生活水準が低く衛生状態が良くなかったと思われる東ドイツ出身者より、西ドイツ出身者のほうがアレルギー疾患が3~4倍多かったそうです。
また、農村地帯のひと、保育園に早くから通っている子、多人数の兄弟がいる子ほどアレルギーが少ないというデータもあります。
子どもが保育園の年少さんの頃は、しょっちゅう熱を出して休んでいたけれど、年長さんになる頃には、ほとんど休まなくなったとか、よく聞く話ですね。
これもいろんな感染症を(発症してなくても)経験して強くなったということです。
つまり幼い頃に色んな微生物や抗原物質と触れ合う機会が多いほどアレルギーが減ることになります。
昔は田んぼなどでどろにまみれて遊んでいた記憶があります。今ではどろんこになれる環境自体が減ってますよね。
社会が清潔になっていくことは喜ばしいことですが、その弊害としてのアレルギーというのは、ちょっと皮肉な気がしますね。
しかし昔ながらの生活、病原体と背中合わせの生活ってのも現実的では無いと思う。
これも「手の届く範囲」で、自然に触れる機会を増やすしかないのだと思います。
そしていつの日か、人類がアレルギーすら克服する日を期待します。
まぁ私の存命中には無理かもしれないけれどね。
私は「手の届く範囲」で、昨年から始めた「小麦断ち」をして、花粉症の季節を乗り越えていきます!
※「小麦断ち」マジおススメ!
最後までお読みいただきありがとうございます!