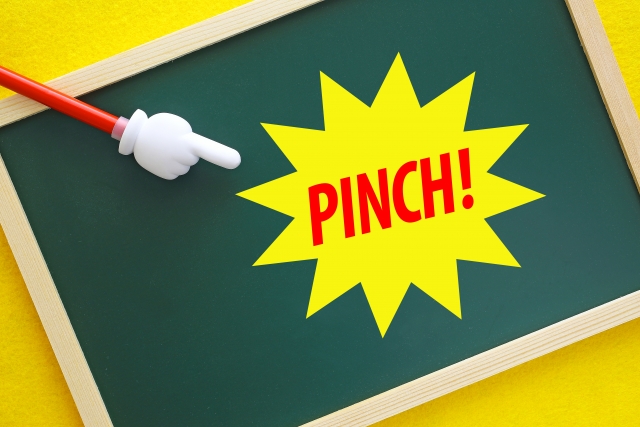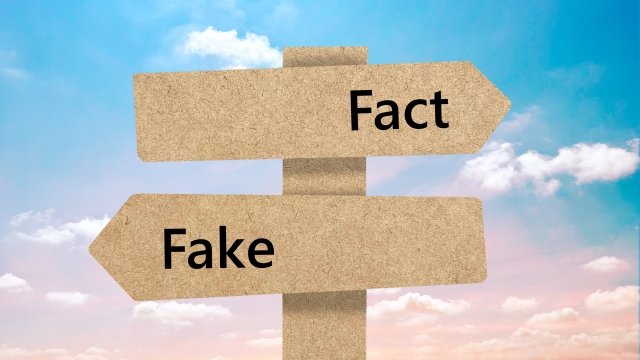こんにちは。
「命」について考えさせられた出来事があったので私見を書かせて頂きます。
昨日(8月2日土曜日)、息子の通っていた中学校でソフトテニスクラブを開催。
台風一過のあまりの暑さに早めに終えることとしました。
クルマで中学校の正門を出ようとしたら、クラブに参加していた子が学校沿いの側溝で何かを見つけた様子。
行ってみると、そこにはカルガモの親子が居ました!
親鳥一羽にひな鳥が8羽。合計9羽が側溝をいったり来たりして、どうにもならない様子。
市役所に電話しても土曜日で担当部署と思われる環境課には誰も居ない様子。
で、仕方ないので110番。
「110番です。事件ですか?事故ですか?」と聞かれるが、「事件でも事故でもないのですが…」
と、詳しい状況を説明する。
ほどなくしてバイクに乗った警察官2名が到着。なんでも1時間くらい前にも通報があったようで、
その時は側溝のふたに隠れてしまったので対応出来なかった様子。
因みに、カルガモがいるような池は地区内にあるのだが、中学校から直線で約1キロの距離。到底そこから来たとは考えにくい。
どうしたものかと言っていると近隣のひとも集まってきて、なんでも4、5日前にも見たような話を聞きました。
私はここで時間切れ。ちょっと仕事があったので現場を後にしたのだが、残った息子に顛末を聴くと、
親鳥は捕まえることが出来ず、ひな鳥だけ保護。警察官が専門家に聞いたところ「ひな鳥を池に放せば親どりは探してくる」とのことらしいので、結局ひな鳥は前述の池に放鳥して終了とのこと。
・ここで疑問 本当に親鳥は探してくるのか?
直線距離で1キロ離れた池にひな鳥を放鳥したらしいが、そもそも親鳥は探せるのだろうか?
息子曰く「俺が池の端に居たとして、父さんは見つけられる?」とのこと。至極真っ当なご意見。
専門家を疑う訳ではないけれど、何処か作為を感じなくもない…
また残酷ながら親鳥的には、今回のひな鳥を諦めて次回(来年?)改めて繁殖を目指すほうが自分自身のリスクを考えても、種を残すという意味においても合理的だと思われる。
残酷な考えだけど、きっと自然はそういった判断で形作られているのだろうとも思う。
・箱庭の中の人たち
以前の記事「箱庭」でお話したのは、個人の認識する世界はその個人の箱庭である的な話なんですが、
集団が形成する、例えば市町村や県、国家、地球全体も、住む人たちにとっての「箱庭」。
その中でひとも動物もあらゆる生物が生きているのであるが、ひとは知恵を授かってしまったがために、文明を築き他の動物たちに先んずることが出来ました。
その文明はひとを豊かにしてきたのは間違いないのだが、同時に自然の摂理から遠ざかってしまっているように感じます。
人類が作った社会、もしくは道徳的な考え方では「取り残されたひな鳥は可哀そう」。
私も勿論そう思います。だからこそ110番に電話してなんとかしなければ…と考えたのですが、
ふと思い止まると、これもひとのエゴなのかと感じました。
残酷な話ですが、ひな鳥が生き永らえなかったとしても、何処かで何かの生物の糧にはなる筈です。
だからこそひとは手を出すべきではない。ようにも思います。
つまり、ひとは快適な箱庭を作ってそこに住んでいるからこそ、その判断基準・道徳観でモノを見る。
可哀そうなひな鳥には何とか生きて欲しいと思うのは間違いでは無いと思います。
しかしそういった価値観は時として自然の摂理に反しているのかも知れません。
・しかし自然からひとは外れたと考えることこそ傲慢
この可哀そうなひな鳥たちも、実は我々とあまり変わりは無いのかも知れません。
ひとが産まれてから教わるのは、ひとの社会の中で生きる術です。そこには自然というファクターも当然ありますが、
所謂サバイバル的なことはあまり教わらないと思います。
そして、先日の津波警報や過ぎていった台風の前では、ひとは無力。勿論みんなで作った箱庭にも災害に対する備えはしている面もあるんだけれど、
それをもってしても克服なんてできやしない。
「万物の霊長」なんて言ってるひとこそが、驕った考えなのではないのかな、なんておもいました。
勿論、ひな鳥たちが無事育ってくれることを願わずにはいられないんだけれど、
それをどうにかするのは、我々が決めていいことではないと思う。
そしてひとは、社会の中でも、生物の中でも、謙虚さは忘れてはいけないのであろう。
最後までお読みいただきありがとうございます!