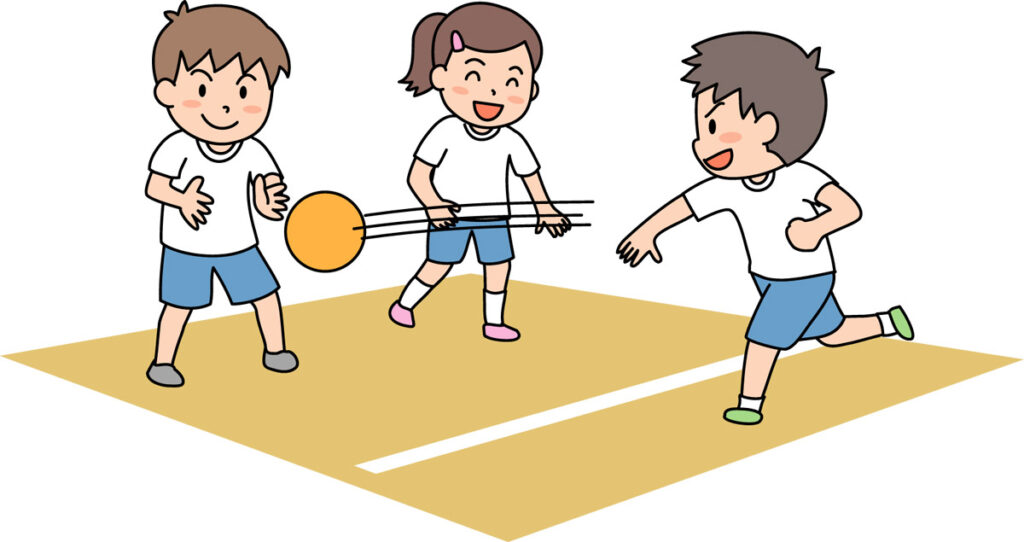こんにちは。
先日、息子の中学校卒業式がありPTA会長として祝辞を述べさせて頂きました。
その中で私が書いておきながら自分で「おかしい…」と思ってしまった言葉があります。
それは「義務教育」
・そもそも義務教育とは?
挨拶文の中で「みなさんは本日、義務教育を終えます」とお話したのですが、祝辞の直前になって、
「子どもたちに何の義務があるんだろう?そもそも子どもたちにあるのは『教育を受ける権利』な筈。」と思い至りました。
もっと早く気が付けば良かったのですが、祝辞直前の、しかも式典最中にふと疑問に思ったのですが、修正能力の無い私であり、また文面から意図する意味とは齟齬が無いと判断してそのまま祝辞を述べさせて頂きました。
ここは反省しています…
さて、何の疑いもなく「義務教育」と使っていますが、どんな義務なのでしょう?
日本国憲法26条に以下のように定められています。
第26条
1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
子どもたちにあるのは「教育を受ける権利」であり、「教育を受けさせる義務」は保護者にあるのです。
つまり保護者にとっての「教育の義務」であり「義務教育」とは間違った言い回しなように思います。
あたかも子どもたちに義務があるような言い回しの「義務教育」。
勿論、その辺りはキチンと定義されているのですが、世間一般の認識はちょっとしたズレもあるように思います。
冒頭の挨拶の一節「みなさんは本日、義務教育を終えます」というのは、厳密には間違っていて、
「みなさんは本日、保護者さんが義務付けられている教育を終えます」と言うべきなのかと思います。
・教育を受ける権利
子どもたちに限らず、すべて国民はひとしく教育を受ける権利を有していると憲法に明記されています。
我々大人もその権利があるのです。
専門的な事柄を改めて学び直しても良いでしょう。一般的ではないにしても社会人から大学に通っても何ら問題ないのです。
・一生学び
これも卒業式の祝辞でお話したことですが、「ひとは一生学びである」ということ。
学業や職能の技術習得で改めて学校に通ってもいいでしょう。
大人たる我々は、実社会・実生活の中でこそ「学び」を得るべきなのだと思います。
日々の気付きや、大切なこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、何からでも学びを得ることが出来る。
大切なのは、そういった「自分以外は全て師である」といった心持ちだと思います。
経験や年齢が邪魔してなかなかそう思えなくなってしまいがちですよね…
でもそんな安いプライドを捨てると、見えてくるものもあろうかと思いますよ。
・学び=真似
「学び」とは「真似る」、「まねび」が語源とされています。
若い頃は年長者を「真似る」ことからだんだんと自分なりの「型」が出来てくるのです。
であれば、我々大人も全く同じ。歳を重ねて更に「真似る」
年齢と共に残された時間は確かに短くなってくるのですが、そういった謙虚さはとっても大事だと思います。
つい「最近の若いヤツは…」とか思いがちですが、そこにも必ず「学び」はある。
若いひとを「真似て」も問題なんてないと思います。所謂「痛い」と笑われてもそれも「学び」。
どんどん「真似」して、一生成長していきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございます!