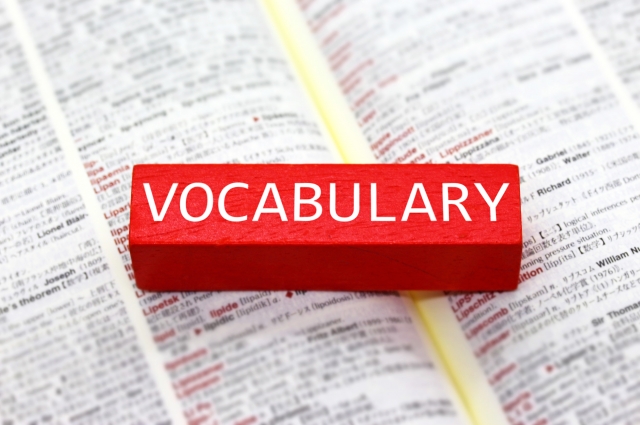こんにちは。
今日7月17日は「東京の日」。
これは1868年(明治元年)のこの日(新暦では9月3日)、明治天皇の詔勅「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」(えどをしょうしてとうきょうとなすのしょうしょ)により正式に布告したことに由来します。
まさにこの日、日本の首都が大きな転換点を迎えたのです。
・何故「東京」?
まぁ読んで字のごとくなんですが、「東の京(みやこ)」という名が示すように、
新たな首都を旧都・京都に対して「東の京都」と位置づけたのが「東京(とうけい)」。
実際、布告当初は「とうけい」と読まれることもありましたが、やがて現在の「とうきょう」に定着します。
この改名には、単なる地名変更にとどまらない、新政府の明確な国家構想がありました。
幕府の旧政庁である江戸を新政府の中心とすることで、明治維新の「体制転換」を象徴させたかったのです。
しかも地理的に東にある東京は、近代化・欧米化という「未来志向」を象徴する地名として、象徴的な意味を帯びるようになりました。
東京という名前には「近代日本の象徴」という側面がありますが、だからといって江戸のすべてを否定した訳ではありません。
たとえば東京の区割りの多くは江戸時代の武家屋敷や町人地の名残をとどめています。
「四谷」「麻布」「日本橋」といった地名も、江戸の時代から続いてきたそのもの。
つまり「東京」は、江戸を捨てたのではなく、「江戸を進化させた都市」でもあるのです。
子どもの頃、東京と言うと「全ての道が舗装されていて、高い建物が沢山建っている」というイメージで実際その通りでした。
私の家の近所はまだ舗装されていない道もあったりしました。
なので「東京」と言うとイメージ通り「都会」「発展している」といった印象でした。
事実、今や東京は世界有数のメガシティとして人口・経済・文化の中心地に成長しました。
明治元年に「東京」と名付けた人々が、現在のこの姿を想像していたかどうかはわかりません。
けれども、彼らが「未来」を向いて名付けたことは確かだと思います。
東京という名前にはいまもなお、明治の人々の志が息づいています。
過去を引き受けながら、未来へと前進する都市。そんな姿勢が、東京の、そして日本の本質なのかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございます!